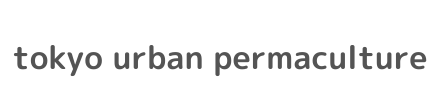最近は戦争についてよく考えている
みんなはどうかな?
僕の今の信じていることは
戦争や暴力を止めるためには
・日々の意識(あり方)
・日々の生活(暮らし方)
・日々の社会との関わり(政治、経済、含め)
をかなり意識的に共生(つながり)の世界観に
変えていくのが一番可能性がある方法
(それを、「ガンジーの氷山」ってよんでいる)
難しいけど、そこに向けて
歩み続ける協同体が
平和な未来を実現するんじゃないかな?
一緒にその道を歩もう!
さて、アクティビスト仲間の鈴木菜央に教えてもらった、
心が動くパワフルな話し
*以下、ブログ【あちたりこちたり】の「あるジャーナリストが書き残したものー花森安治の「見よぼくら一銭五厘の旗」という記事より。
花森安治の「見よぼくら一銭五厘の旗」
花森 安治
ハナモリ ヤスジ
はなもり やすじ 編集者 1911・10・25~1978・1・14 兵庫県神戸市に生まれる。東大在学中、扇谷正造、杉浦明平らと帝大新聞の編集に携わり、戦後1948(昭和23)年、「暮しの手帖」を創刊、雑誌の全面に花森の手と息吹がかかっていた。
掲載作は1970(昭和45)年10月、「暮しの手帖」第2世紀8号に掲げた胸にしみるマニフェストである。なお、改行の仕方について今や筆者に確認をとれない微妙な点があり、雑誌初出時の改行(組体裁)のママに従っている。
見よぼくら一銭五厘の旗
美しい夜であった
もう 二度と 誰も あんな夜に会う
ことは ないのではないか
空は よくみがいたガラスのように
透きとおっていた
空気は なにかが焼けているような
香ばしいにおいがしていた
どの家も どの建物も
つけられるだけの電灯をつけていた
それが 焼け跡をとおして
一面にちりばめられていた
昭和20年8月15日
あの夜
もう空襲はなかった
もう戦争は すんだ
まるで うそみたいだった
なんだか ばかみたいだった
へらへらとわらうと 涙がでてきた
どの夜も 着のみ着のままで眠った
枕許には 靴と 雑のうと 防空頭巾を
並べておいた
靴は 底がへって 雨がふると水がしみ
こんだが ほかに靴はなかった
雑のうの中には すこしのいり豆と
三角巾とヨードチンキが入っていた
夜が明けると 靴をはいて 雑のうを
肩からかけて 出かけた
そのうち 電車も汽車も 動かなくなっ
た
何時間も歩いて 職場へいった
そして また何時間も歩いて
家に帰ってきた
家に近づくと くじびきのくじをひらく
ときのように すこし心がさわいだ
召集令状が 来ている
でなければ
その夜 家が空襲で焼ける
どちらでもなく また夜が明けると
また何時間も歩いて 職場へいった
死ぬような気はしなかった
しかし いつまで生きるのか
見当はつかなかった
確実に夜が明け 確実に日が沈んだ
じぶんの生涯のなかで いつか
戦争が終るかもしれない などとは
夢にも考えなかった
その戦争が すんだ
戦争がない ということは
それは ほんのちょっとしたことだった
たとえば 夜になると 電灯のスイッチ
をひねる ということだった
たとえば ねるときには ねまきに着か
えて眠るということだった
生きるということは 生きて暮すという
ことは そんなことだったのだ
戦争には敗けた しかし
戦争のないことは すばらしかった
軍隊というところは ものごとを
おそろしく はっきりさせるところだ
星一つの二等兵のころ 教育掛りの軍曹
が 突如として どなった
貴様らの代りは 一銭五厘で来る
軍馬は そうはいかんぞ
聞いたとたん あっ気にとられた
しばらくして むらむらと腹が立った
そのころ 葉書は一銭五厘だった
兵隊は 一銭五厘の葉書で いくらでも
召集できる という意味だった
(じっさいには一銭五厘もかからなか
ったが……)
しかし いくら腹が立っても どうする
こともできなかった
そうか ぼくらは一銭五厘か
そうだったのか
〈草莽そうもうの臣〉
〈陛下の赤子せきし〉
〈醜しこの御楯みたて〉
つまりは
〈一銭五厘〉
ということだったのか
そういえば どなっている軍曹も 一銭
五厘なのだ 一銭五厘が 一銭五厘を
どなったり なぐったりしている
もちろん この一銭五厘は この軍曹の
発明ではない
軍隊というところは 北海道の部隊も
鹿児島の部隊も おなじ冗談を おなじ
アクセントで 言い合っているところだ
星二つの一等兵になって前線へ送りださ
れたら 着いたその日に 聞かされたの
が きさまら一銭五厘 だった
陸軍病院へ入ったら こんどは各国おく
になまりの一銭五厘を聞かされたで
ーーーーーーー