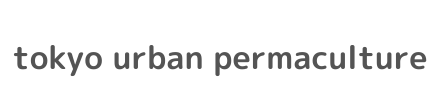仲間のフィルとカイルと今年開催したパーマカルチャーデザインコース(PDC)中に取材があったソトコト onlineの記事が公開された。
しかも同時に3本も!!!
記事を書いたのは、数年前のPDCを受講した鍋田ゆかり。
こうやって、文化ができていく。
Check it out!
「パーマカルチャー」という言葉を聞いたことはありますか? ここでは、2023年に千葉県鴨川市で開かれた「PDC(パーマカルチャー・デザイン・コース)」の様子を交えながら、パーマカルチャーの言葉の意味とその内容について、実践者たちの言葉を借りながら紹介していきます。
パーマカルチャーについての記事(3本)
・「パーマカルチャー」って知ってる? 消費者から創造者になって循環する生き方
・パーマカルチャーに魅せられ、消費者から創造者になった3人の暮らし
・パーマカルチャー実践者に聞く、すぐに始められるパーマカルチャー的行動6例
この記事に向けて、3人の「パーマカルチャーとは?」への回答
フィルさんにとってのパーマカルチャーは「一つの道具」
フィルさんは、「どうやったら地球を破壊せずに生きていけるか」を探し求めていると言います。「パーマカルチャーのやり方」にこだわらずに自然をよく観察し、自然を先生として、そこから学びを得てフィールド作りに生かしています。
できるだけ自然を破壊せず、ゴミを出さず何かに利用するという考えで、庭師が剪定して出る大量の葉っぱ付きの枝をフィルさんが引き取って、フィールドにあるコンポストステーションに入れます。葉っぱや枝が少しずつ発酵していく発酵熱で、2~3週間は40度のお湯を作ることができる「コンポスト風呂」の熱源として利用。最終的に、発酵したコンポストは堆肥として畑に入れ、そこで野菜を育てます。
身の回りの環境をよく観察することで、不要に思えるものでも暮らしに役立つものに変換して利用することができます。
フィルさん「ぼくにとっては、どうやって地球を破壊せずに人が生きていけるかを探求する旅のなかの一つの道具として、パーマカルチャーがある」
カイルさんにとってのパーマカルチャーは「五つのジェイ」
カイルさんが言う「5J(ファイブ ジェイ)」は、自給、自立、循環、持続、Joy(喜び)の五つです。パーマカルチャーをするためにどこかに移動する必要はなく、今いる場所の資源を生かして生活することが「平和への一歩」だと言います。無いからほかの土地やほかの国から手に入れようとすると、資源の奪い合いになって戦争につながってしまうから。今ここにあるものを生かすことが大切ですが、全てを自給することは無理なのでコミュニティが必要になります。
カイルさん「コミュニティのなかで、お互いに貢献したり助けたり。それができたら本当の自立になる。日本のパーマカルチャーの軸は、里山でも都会でも『循環』だと思う。循環を取り戻すと、持続可能にできる」
カイルさんのフィールドは自給率が高く、米、味噌、醤油、野菜や果物だけでなく、建物も9割はその土地にある山の木を使って建てています。これから電気も自給して、「資源を外から奪わない」を実践し続けていますが、苦労ばかりだと続かないので「Joy(喜び)が必要。カイルさんにとってのJoyは、夕方に自分の敷地を歩いて散歩をすることだそうです。
海さんにとってのパーマカルチャーは「豊かな暮らしの道」
私たちは基本的に、仕事をしてお金を稼ぎ、そのお金で誰かが作った物を購入して消費する“消費者”ですが、パーマカルチャーは「自分で自分の理想を作る(創造者になる)ことで、やればやるほど楽しくてパワーが湧いてくる」と海さんは言います。
海さん「家を建てることに憧れていたから、雑誌を見て建ててみちゃった。電気を自給したくてやってみたら、発電できちゃった」
新しいことに挑戦するのは大変ですが、やっていくうちにその大変さが「楽しい」に変わっていく。一つの専門家になるのではなく、暮らしに必要ないろいろなことができるようになっていくのは、百のことができるようになる「百姓の世界」と似ています。
海さん「パーマカルチャーは、出費を減らして豊かさを増やすのが特徴。循環で心や時間、お金の余裕ができる。地球を楽しむために人は生きていると思うから、そこを取り戻せる人生の道」
記事の全文はここ